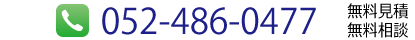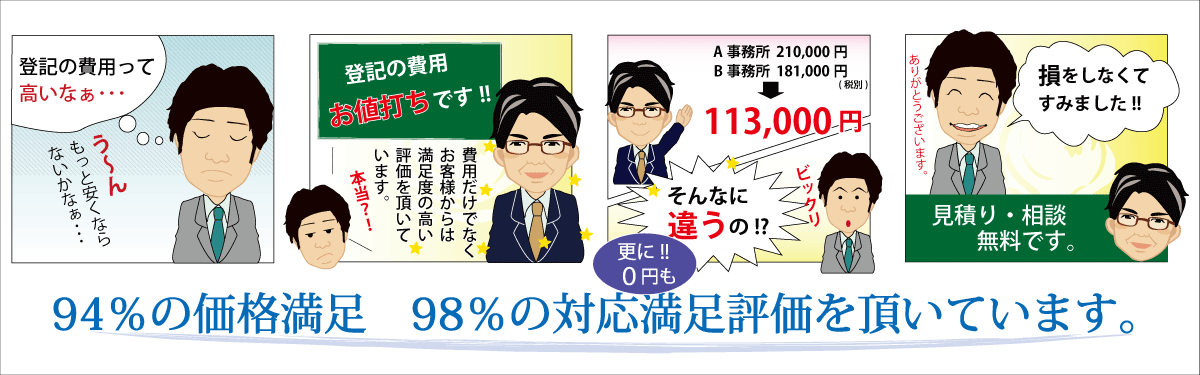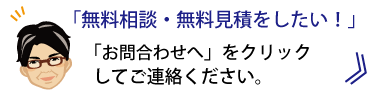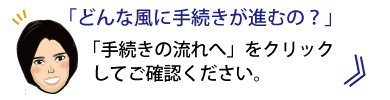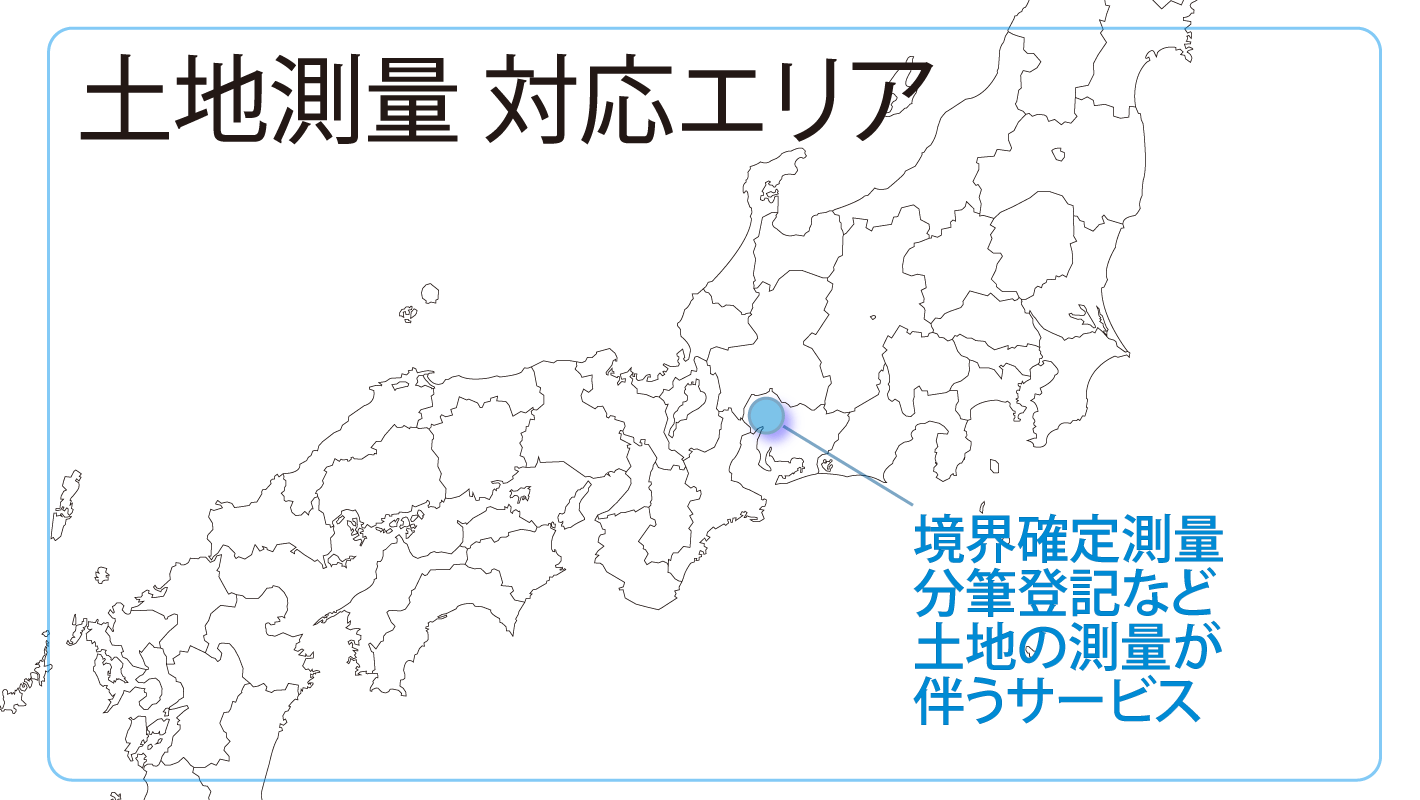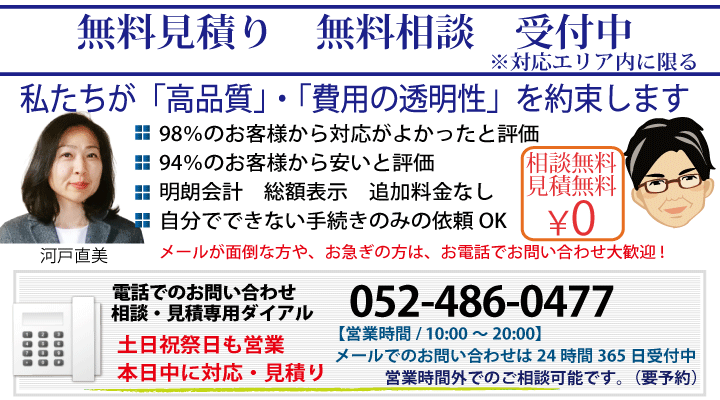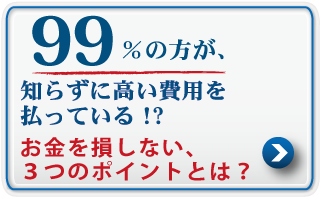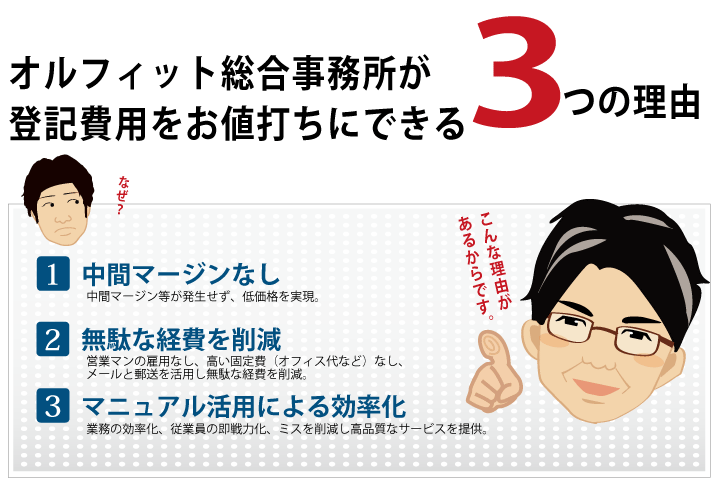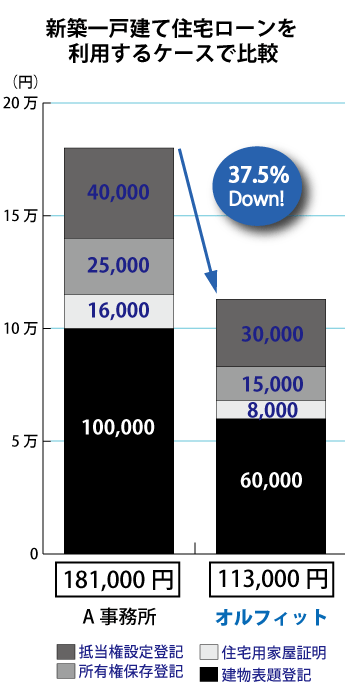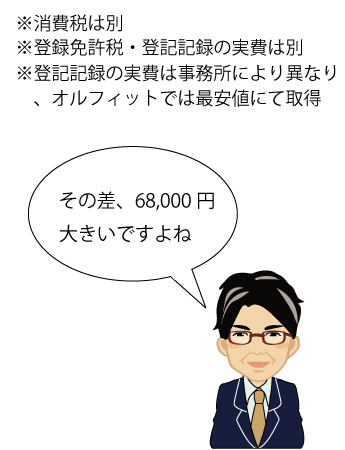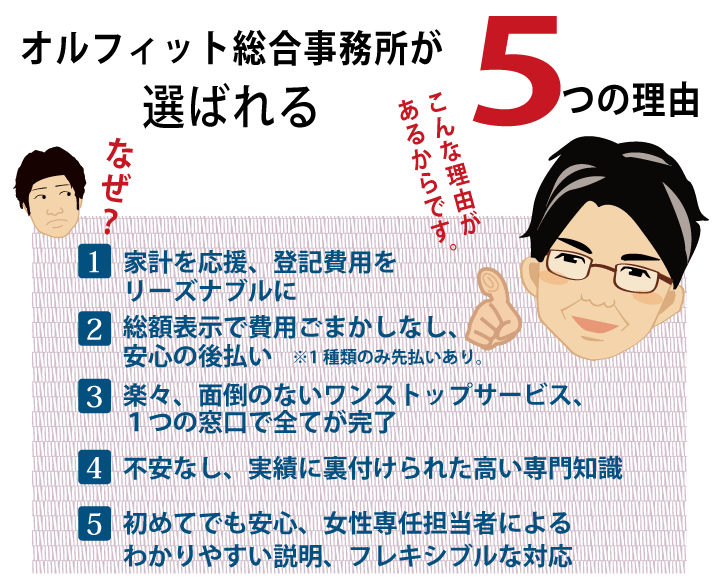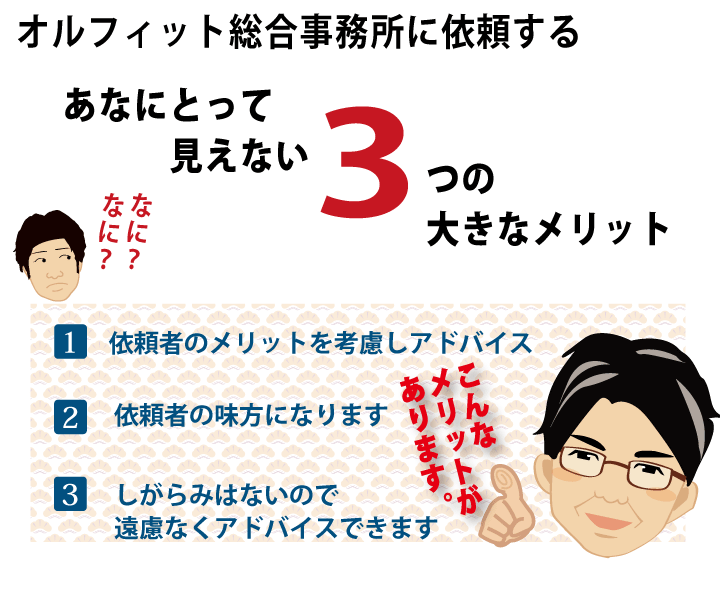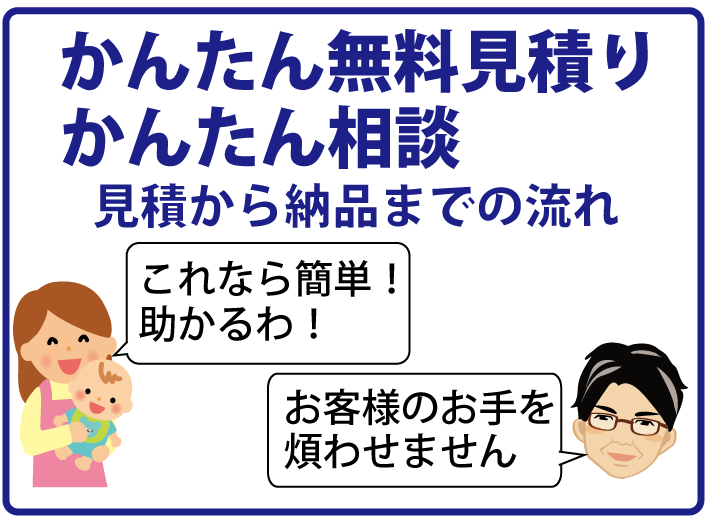GPSは世界中に展開する米軍が作戦を行うために情報収集の道具として誕生しました。
具体的には、艦船や航空機などの位置を特定する為の衛星航法システムです。
GPSは1970年代に計画と開発が開始され、当初の予定では1984年の完成を目指していました。
しかし、様々な理由により完成が遅れましたが、人工衛星24個全部の打ち上げが完了し、1993年12月に現在の運用形態になりました。
しかし、当初GPSは、軍事目的に特化していた為、SA(selective availability)と呼ばれる、精度劣化操作がされていたため、精度が悪く利用制限されていました。
ところが、2000年5月2日に国防上の理由から施されていたSAが突然解除され測位精度は大幅に向上しました。
利用制限が解除されたことにより、精度の高い測量が可能となり、国土地理院は全国1200点以上に電子基準点を設置し高性能GPS受信機と通信システムが装備しました。
そして2002年から、電子基準点のリアルタイムデータの提供が始まり、現在931点の電子基準点のリアルタイムデータが利用可能となっています。
これらにより、様々な分野での研究に広くGPSは活用されています。
その他には、旧ソ連がGPSに対抗するために1980年代に「グローナス(GLONASS global orbiting navigation satellitesystem)」という計画をスタートしロシアが運用しています。
しかし、同システムの安定性には未だに懸念があるようです。
1997年に、欧州連合(EU)と欧州宇宙機関(ESA)が中心となり、ガリレオ計画(Galileo project)を発表し、2008年の運用開始を予定しています。
日本においても準天頂衛星計画があります。
これらの衛星を利用したシステムができれば現在のGPSより高度なシステムができるでしょう。
そして、トプコンが2005年6月にGPS衛星29機とGLONASS13機の衛星を利用し新しい測量機器を発表しました。
他の測量機器はGPS衛星のみを利用した機器ですが、トプコンの新しい測量機器はグローナス衛星を利用することにより測量精度向上及び従来GPS測量が苦手とした場所においても多くの衛星を利用することにより安定した測量を実現しました。
この技術は素晴らしいものであると同時にガリレオ計画によって今後打上げられ利用できるようになる衛星により従来よりも更に優れた測位システムが実現されることを期待します。